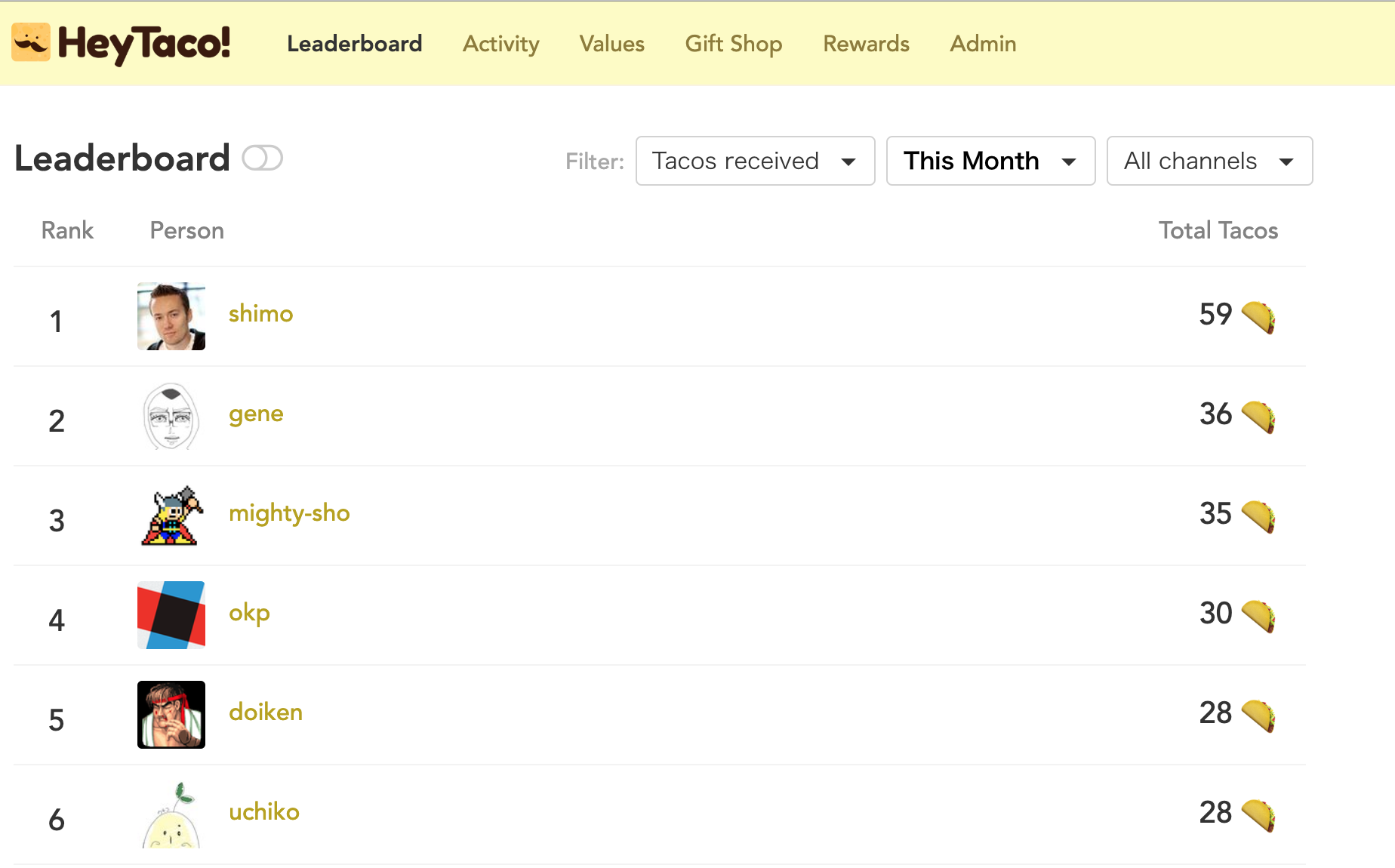現状から始める 〜 ITIL4に基づいて考える 〜

はじめに
こんにちは。kuwaです。
前回はITILで定義されている7つの従うべき原則のうち、「価値に着目する」について書きましたが、今回は「現状から始める」について考えを整理する内容とします。
ITILや従うべき原則については前回の記事をご覧ください。
前回の記事はこちらです。
※当記事は、あくまで一つの見解です。
現状から始めるについて掘り下げてみる
まず、「現状から始める」の説明は下記がされています。
新しいものをゼロから開始、また構築するのではなく、すでにある利用可能なものを活用することを検討します。
引用元:https://peoplecert.jp/ITIL4_c_gp.html
現行のサービス、プロセス、プログラム、プロジェクトおよび人材などの中に、求められる成果を生み出すために利用できるものが十分に存在している可能性があります。
現状に直接目を向けて調査し、完全に把握する必要があります。
現状から新しいものを作成するという前提での原則になります。
現状を評価する
先ほどの説明には、新しいものを作るときはすでにある利用可能なものを活用するよう検討する記載がありました。
新しいものを作ろうとするときには、現状を全て取っ払って新しいもののことばかり考えたくなってしまうかもしれませんが、現状の中には評価をされている内容、改善できる内容と混在している場合があります。
現状のうちから評価されている内容がなぜ評価されているのか、改善すべき内容がなぜ改善すべきとされているのかの理由やそれらが求められる将来像に適しているかを把握すると、新しいものを作る際の方針・計画が細かく定まると考えられます。
また、それを再現、発展させられるのか、可能な場合はどのような方法で達成可能かについても検討します。
一方で、現状を評価せずに新しいものを作った結果、評価されている内容を悪化させてしまう可能性があります。皆さんも以前の方が使いやすかったなと、新しくなったものに対して思ったこともあるのではないでしょうか。
作った後でそういった状況に陥っていたことを気づいた際には遅いと思いますので、計画前の時点から現状を評価しておくことは重要です。
測定の役割
現状を評価するための過程として、測定があります。測定結果と現状に関する知識から評価を行います。
また、何かデータを参照するのではなく、実際に現状を見ることで求められる将来像へ向かうための現状の評価が正しいものに近づきます。
注意点として、測定は測定自体が結果に悪影響を与えないような形で行います。測定されていることを意識してしまうと、その基準に沿った内容に結果を誘導してしまうようなことも考えられます。グッドハートの法則という法則でも述べられているようですが、その基準が目標となってしまうと、結果、それはいい基準ではなくなります。偏向する要因をなくして測定を正しく行い、現状を正しく評価することがより良いシステムにつながると考えられます。
おわりに
新しいものを作る上で現状の評価、測定と、その測定基準や方法を重視したいという内容でした。
あらゆるものが存在する現代で全く新しいものを作り出すというのは難しいと考えていますが、一方であらゆるものがあるから参考にできるものは沢山あり、それらを正しく捉えて使用していくことが良いものを生み出すことに繋がると考えます。
整理してみましたが、前回の「価値に着目する」の視点を持っておくと現状の評価すべき点がより明瞭になるかもしれないと感じました。
以上です。ご一読いただき、感謝いたします。
参考資料
https://peoplecert.jp/ITIL4_c_gp.html